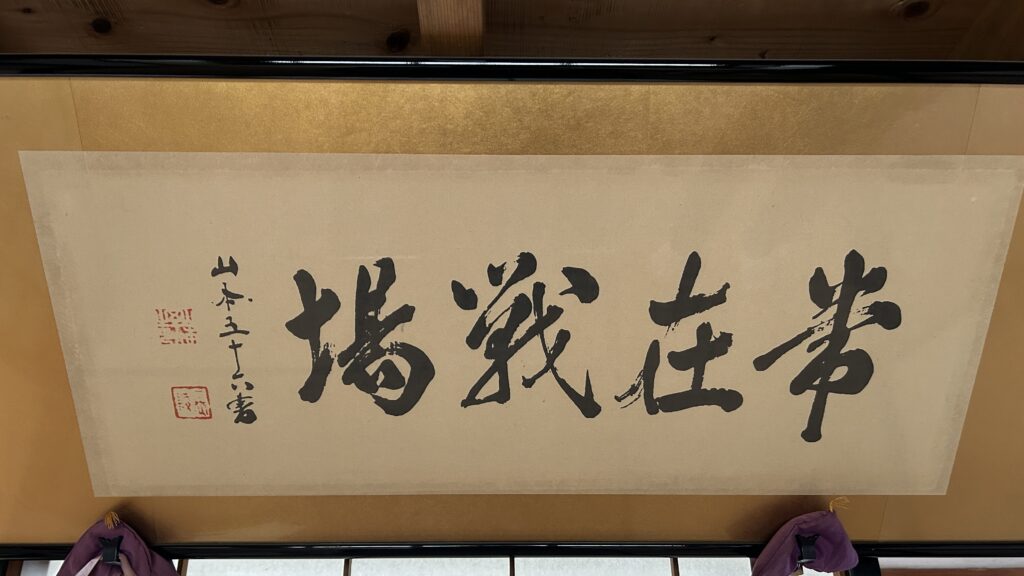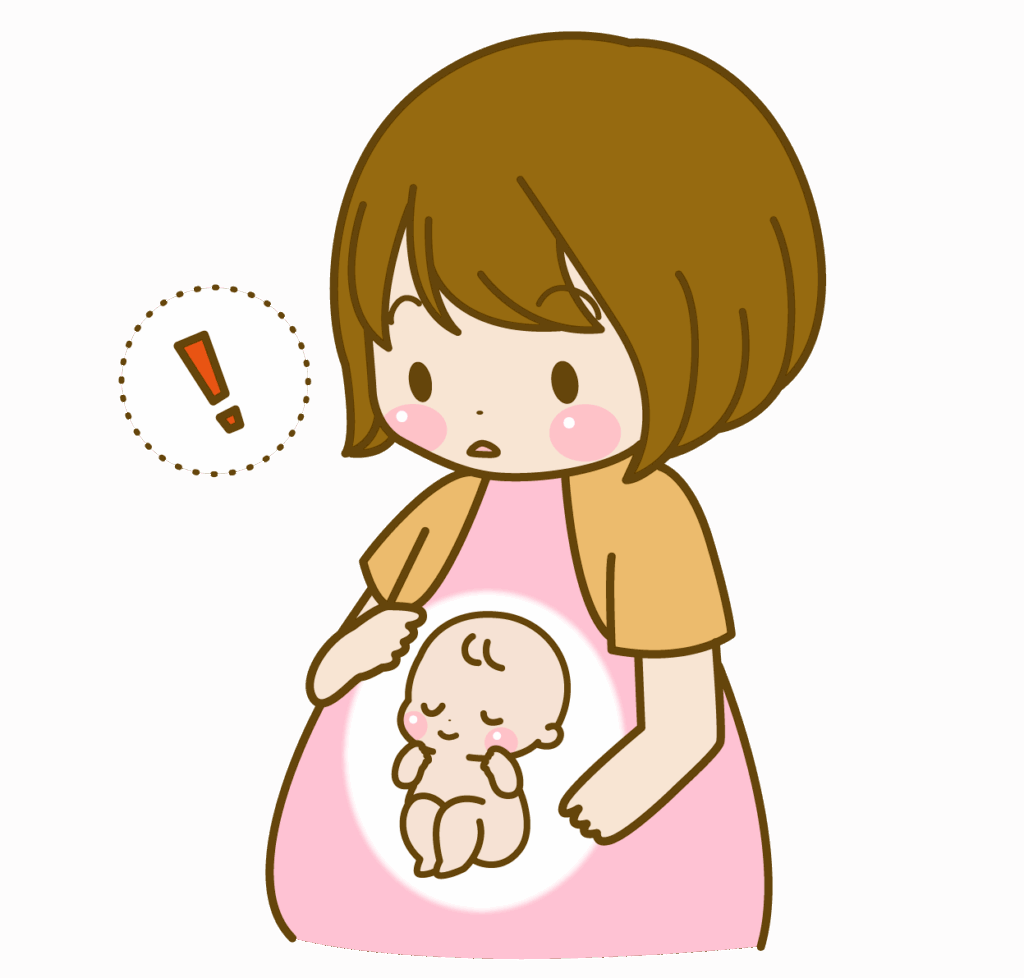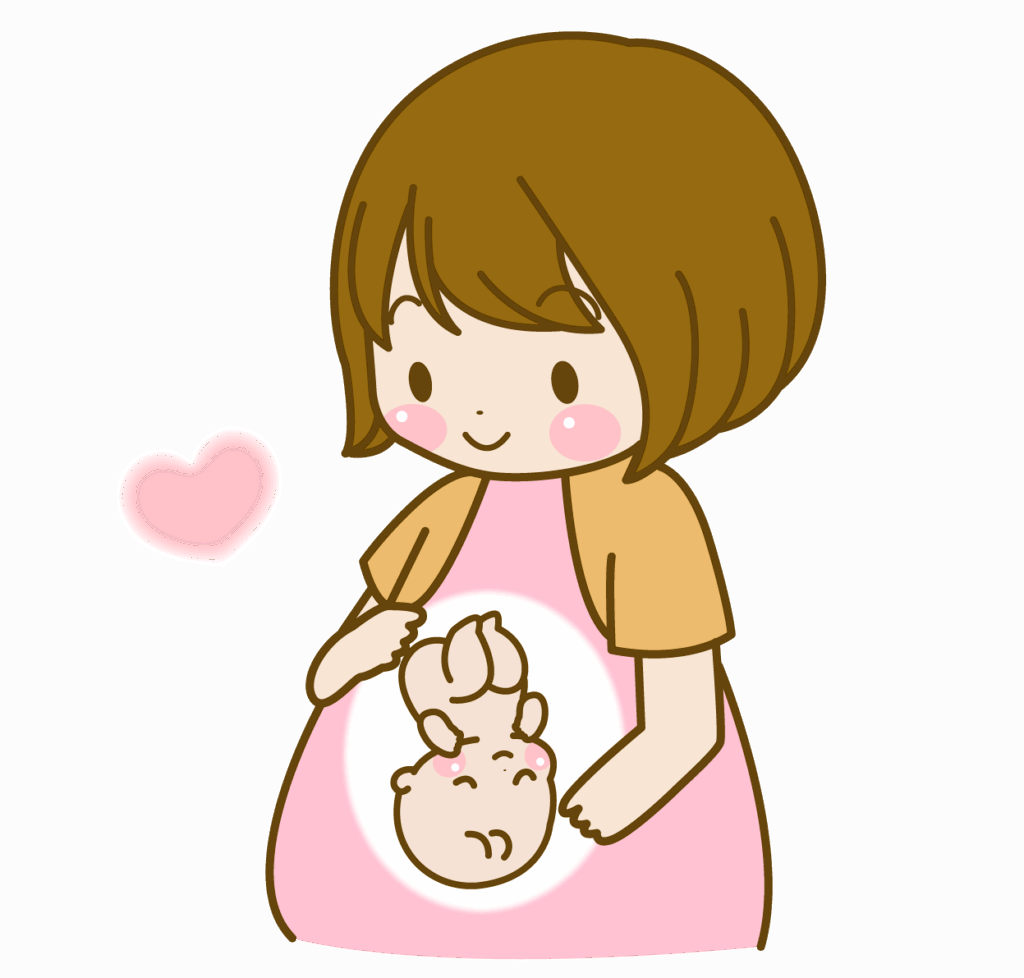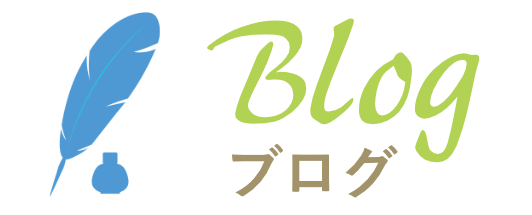『戦士の休息』『天使の休息』
鍼を受けたことのない方は不思議だと思われるかもしれませんが、鍼を受けている最中に寝てしまう方が一定数おられます。
『マッサージなら理解るけど、鍼なのになぜ!?』『本当に!?』と思うかもしれませんが、事実なのです。
最初から寝てしまう方、途中から会話が途切れて寝てしまう方、一瞬夢の中へ行かれる方など様々です。
(中には寝ていたことを悟られないようにされる方も…(^^;))
このような状態を勝手ながら密かに『戦士の休息』また『天使の休息』と呼ばせていただいております(^^)
鍼の臨床でこのようにスヤスヤと寝ている状態を目にする度、思い出す曲があります。
その曲とは…
岩崎宏美さんの『聖母たちのララバイ』と久松史奈さんの『天使の休息』です。(懐かしい名曲ですね。)
御存知の方も多いと思います。
(以前、銀座の某ショップにて岩崎宏美さんをお見かけしました(^-^) 気さくに店員さんとお話しされていて、笑顔がチャーミングでとても素敵でした(^^♪)
西洋医学は厳格な『父性』のイメージがありますが、鍼療(東洋医学)には『母性』の要素を感じます。
それ故か鍼療中『聖母たちのララバイ』には共感するところがあります。
歌詞のような『母性』までは真似できませんが、歌詞の内容にはとても共感してしまいます。
普段の日常で、みなさんお一人おひとりが見えない何かと戦っていると思います。
仕事や家庭も子育ても、趣味や遊びも、みなさん一生懸命です。
《Bar》や《Bartender》が《優しい止まり木》であるように
鍼に来たときも、再度羽ばたけるように、少しでも翼を休めていただけたらと思っています。
表には出しませんが(^^; そう思って鍼療に臨んでおります。
『天使の休息』は《Cheer up song》ですねp(^-^)q
次の一歩を踏み出す前の大切な休息。がんばり続けることってできないから
適度に休息をして『次、行ってみよう!!』って感じですね。
日々の仕事や家庭、子育てや趣味にと懸命な方々の束の間の休息…
再度飛び立つのに必要な休息…
鍼治療は敢えて『自律神経!!』と声高に標榜しませんが(基本中の基本なので)
鍼治療の本質のひとつが『自律神経』への作用です。
大抵の方は交感神経優位の状態ですので、鍼をすると副交感神経に作用します。
副交感神経優位になると、心拍数や血圧が下がり、身体がリラックスして休息モードに入ります。
そのため、その方の疲労具合などによっては鍼の最中に寝てしまうことがあるのです。
鍼の最中に寝てしまうのは、回復のために必要な反応でもあります。ご安心ください。
湿度が高く、天候も不安定なこの季節
鍼による効果で心身共にリラックスして免疫力を高めてみましょう。
心身は自分で思っている以上に休息(=鍼療)を必要としているかも知れません。
スポーツなどで痛めた身体も休息(=鍼療)が必要です。
みなさんも
とりあえず『鍼』して『呑んで』
『戦士』も『天使』も《休息》しましょう(^^)/
《岩崎宏美 公式YouTubeチャンネルより》
《久松史奈 オフィシャル YouTube チャンネルより》
#鍼灸esmeraldabrisa
#栃木市鍼灸院
#栃木市万町
#戦士の休息鍼灸
#天使の休息鍼
#岩崎宏美
#岩崎宏美聖母たちのララバイ
#久松史奈
#久松史奈天使の休息
#鍼灸自律神経