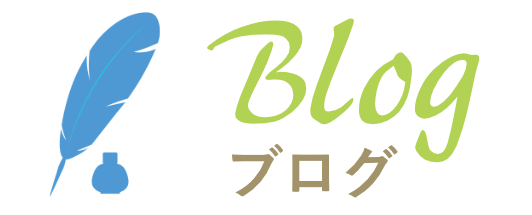『病名』と『呪(しゅ)』

先日、自分の身体の痛みや症状が何なのか。原因が不明で、どこの病院へ行っても病名が特定されずに苦しまれている方がいました。
ようやく自分の症状に診断がついて病名がハッキリして、とても安堵されていました。
理解されない苦しさや、受け入れてもらえない孤独感がどれほど辛いことなのかと云うことが伝わってきました。
これはテレビの中でのお話です。(総合診療科のお仕事はとても大変で大切なお仕事だと尊敬しております。)
劇中でも『病院では、病名が付かないと健康保険が適応にならない。』と語られていました。
病名を付けたり、病気の診断をするのは医師にしか認められていない権利なのです。
どこに行っても、自分の痛みや症状が判らずに苦しみ、自分の辛さが判別されて安堵する気持ちはとても理解できます。ところがもう一方で、診断されて病名が付くことで病名や病気に『囚われてしまう』方の存在もあると思うのです。
陰陽師である安倍晴明は
『この世で一番短い呪(しゅ)とは名である。』と。
人は名前で呼ばれるから、自分が自分で在ることを理解して受け入れ、その名前の通り振る舞い、その名前のようで在りたい。と自分で自分を縛り付けて行くのだと思います。
「呪(しゅ)とは ようするにものを縛ることよ ものの根本的な在様(ありよう)を縛るというのは名ぞ」
と晴明は話していました。
『呪(しゅ)』によって心の在り方も変わってしまいます。
『病は気から』と云う言葉も、まさに『呪(しゅ)』によって縛られれしまっている典型だと思います。
安倍晴明役では野村萬斎さんが有名ですが…
個人的にはNHK のドラマで安倍晴明役をされていた稲垣吾郎さんのイメージです。
源博雅役は… 映画版の伊藤英明さんですかね…(^^
学問でも、学問の事始めとは『名前を付けること』だと思います。
モノや事象や現象に名前を付け、分類し整理して行く。
名前が無ければ、存在していてもモノや事象や現象と一致させることができません。
鍼灸院では、病名を付けることや診断権がありませんので、患者さんの訴える症状やつらさを聞いて治療方針や症状の改善に努めて行きます。
病名を付けることや診断権がないからといっても、鍼灸師は西洋医学的な病気や疾患の勉強もしていますのでご安心ください。
西洋医学の勉強はもちろん鍼灸師の国家試験にも出るのです(^^;
ちなみに、先述の患者さん。
『線維筋痛症だと思うんだけどなぁ。』と思いながら観ていましたが…
診断の結果、やはり『線維筋痛症』とのことでした。(おっと、医師以外が診断してはいけませんね… (^^; )
東洋医学では病名に振り回されず、人を診ています。
病名に縛られないからこそ、患者さんの状態や訴えが見えてくることがあります。
最近の鍼灸院でも、専門性を打ち出している鍼灸院が増えました。『腰痛専門』や『肩コリ専門』など…
今時のトレンドなのでしょうか…(^^;
鍼灸院と云う場所は基本的には『総合診療科』です(^^; 患者さんの診療科目を問いません。昔からです(^^;
内科的な症状から、整形外科的症状、耳鼻科領域、ストレス性の問題、はたまた婦人科(PMSなど)や産科(安産や逆子など)等々、普段から日常生活で起こり得る、あらゆる症状を扱っています。
専門の診療科目の方が羨ましく思うこともありますが…。
結局身体は繋がっているので、『腰だけに効かせる』とか『肩だけしか治さない』って云うコトの方が難しいと思います。
腰の治療で肩コリも改善されてしまいますし。肩コリの治療でお腹の調子も整ってしまいますし…。
この身体の一部分ではなく全身を診るスタイルも、鍼は『病気ではなく人を診ている』と云うコトにも繋がっていると思います。
(『病気ではなく人を診る』のは鍼治療や東洋医学での超!!基本的なスタンスです。)
昨今の流行りでは無く、二千年以上も前からですね。
『病気ではなく人を診ている』というのは鍼治療の特性でもあると思います。
究極ですね。鍼治療を発明された人も、鍼ととても相性のいい人体の仕組みも。
鍼は人体の仕組みやシステムととても相性がいい。と日々の臨床で感じています。
(鍼灸も病院の診療科目に入れたらと思いますが… 市井で黙々と結果を出すしかありませんね…(^^; )
昔から鍼灸院が基本的に専門性を打ち出さずに総合診療としているのはなぜでしょうか。
それは『日常生活で困るちょっとした身体症状を相談できる場所』であるからだと思います。
症状が進行して、本格的な病気に移行しないように、水際で防ぐ役割が鍼灸院にはあるのだと思います。
それが東洋医学や鍼灸の得意とする『未病治』でもあるからです。
鍼灸院で治療すると云うコトは『病名が付く前に症状が改善されてしまう。』と云うコトです。
もちろん鍼適応外の場合は、専門の病院をおすすめします。
ガマンをして症状が進行してしまう前に。
気になることがありましたら、街の鍼灸院に相談してみましょう。