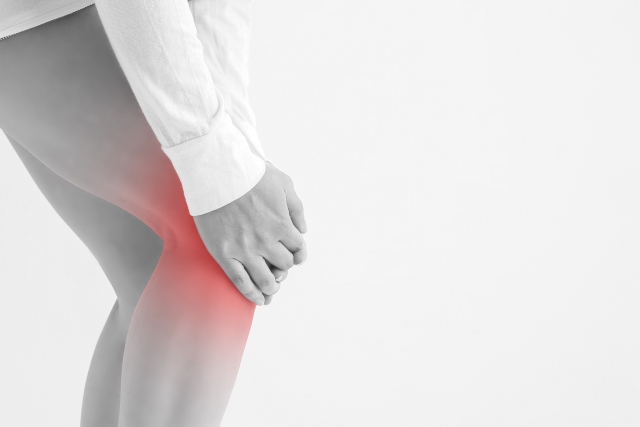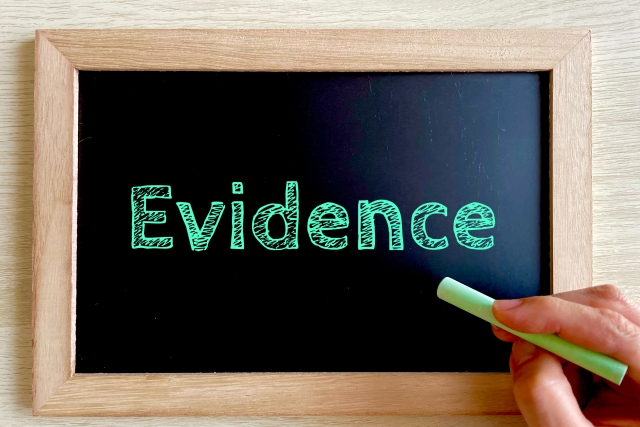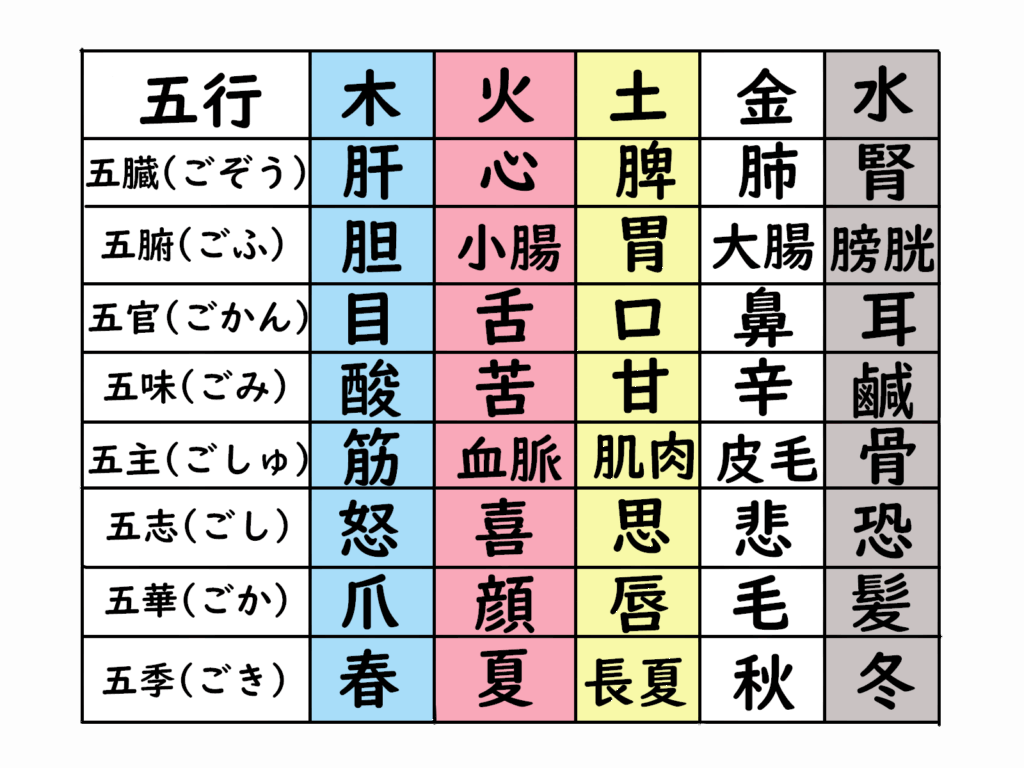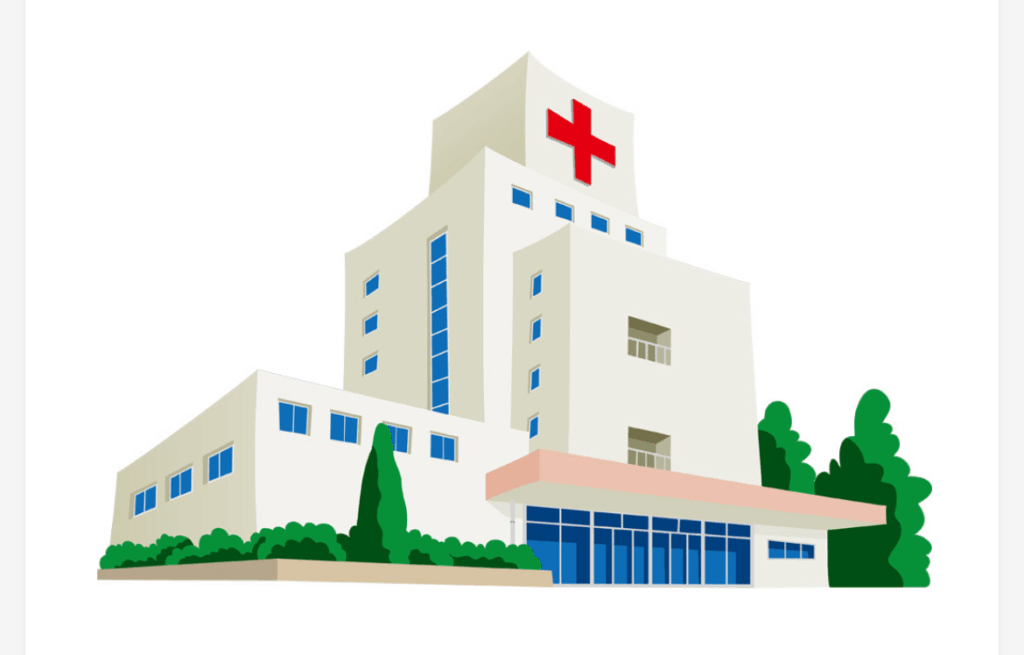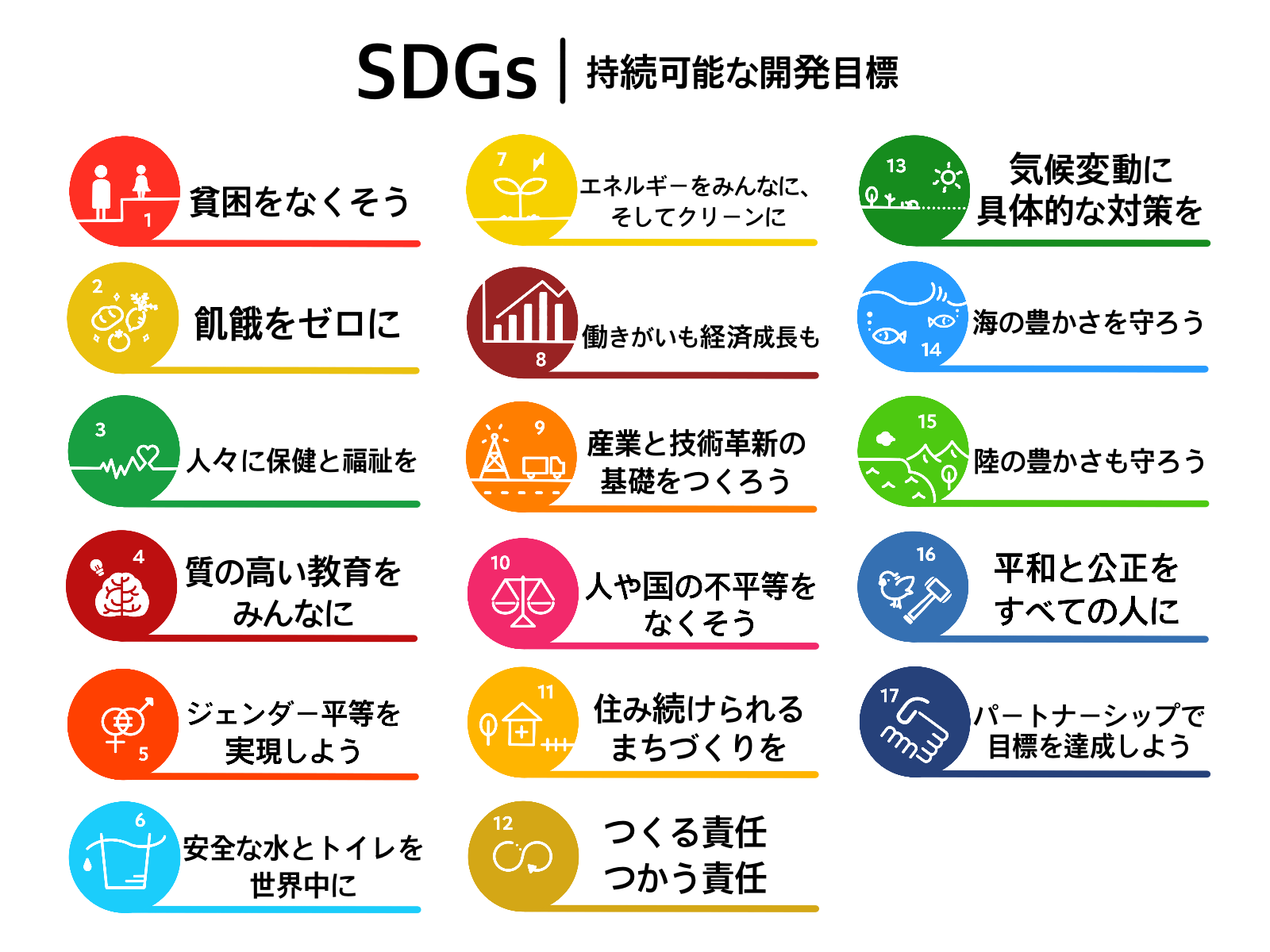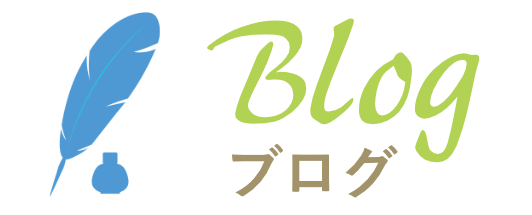『最高の打者(バッター)と最高の投手(ピッチャー)』

昔たまたま見たテレビの企画番組で、とても印象に残った番組がありました。
しばらく前のお話です。仕事から帰ってきて、夕飯を食べながら観ていました。
前回Blogに書いた、『若いカウボーイと中年のベテランカウボーイ』の続編のような内容です。
みなさんも読んでみて、どのような感想をお持ちになるでしょうか。
プロ野球選手で最高の打者の一人が、現役生活を退きました。
引退後に現役選手時代の心残りがどうしてもあって、その心残りを実現させるべく企画された番組でした。
その心残りとは
『小さな息子に、現役中の試合でホームランを打つ姿を見せてあげられなかった…。』
ということでした。
『息子にどうしても、お父さんがホームランを打つ姿を見せたい。』と。
その対戦相手に選ばれたのは、丁度同じ頃に引退した同世代で最高の投手でした。
(番組はいつの間にか両雄の勝負!?と云う形になってました…(^^; )
お互いに現役を退いているので、コンディションを整えるための期間が1か月設けられました。
その1か月の間で、お互いがどのような準備をしていたのか。そこが今回のキモです。
打者の方は、肉体改造に励んでいました。
重いバーベルを持ち上げ、引退した身体に鞭打つかのような激しいトレーニングでした。
ここでふと、
《あれ!? 現役中に激しい肉体改造をすることにより、ケガをしたり故障が多くなったことが引退のきっかけにもなったんではなかったっけ?》と思いました。
そして、自分が高校生だった頃と同じような激しいトレーニングメニューをこなしていました。
今風に言うと『THE 昭和』な感じのトレーニングです。
ここでも、
《過去の成功体験から、絶好調だった高校時代の自分を思い出してその頃と同じようなトレーニングをしているのかな!?》
と思いました。

一方で投手の方はというと…。
引退した中年の肉体と云うことを理解しているのか(耳が痛い…(^^;))
『どのようにしたら、現役を引退した身体に負担なく投げられるのか!?』を考え
『古武術の先生』に教えを求めました。
この辺りは流石ですね(^^;)
さらに、当時は最先端であったスポーツ科学(今では当たり前かもしれませんが)などを1か月の期間中に取り入れていました。
現時点での肉体に『如何に無理なく、効率よく。』を考えた結果のスポーツ科学の導入。
しかも1か月という期間を考えると、限られている中での最大効率化を求めた結果の選択でした。
《老練で老獪な感じと云うか…(^^; その後憧れ続けた志望大学に進学しているので賢いですよね。スタートが全然違いました。これじゃバッターは絶対に敵わないなぁと感じました。》
いよいよ1か月後の勝負の時!! 互いに練習の成果は発揮されるのか!? 結果や如何に!?
家族が見守る中、打席に立つバッター。息子さんにホームランを打つ姿を見せることが出来るのか!?
結局バッターはホームランを打つことが出来ず…。
投手が最後にお情けで甘い球を投げることで、結果ホームランを打つことが出来ました。
結果はともかくとして、注目すべきは『1か月の期間でどのような準備をしたのか?』と云うコトです。
この話題は今でも患者さんに説明する時の一例として、お話することがあります。
ある程度の年齢を重ねた患者さんが
『筋肉を付けなきゃ』『運動しなきゃ』など自覚されたり指導されたりと、競技選手ばりのトレーニングや高負荷の運動などを実践されていることが多々あります。
そのため、身体を壊してケガや痛みを抱えている場合があります。
『健康になるためのトレーニングで、逆に身体を壊してしまう』と云う矛盾です。
いつまでも『若くいたい』『若いつもりでいる』ことは大切なことですが
ベテランにはベテランなりのトレーニングや鍛え方があると思います。
そのためには、先ず自分の状況を冷静に見つめて自覚することから始まります。
そして経験や体験から学んだ知恵を使い、新しい情報を取り入れて
『賢く、効率的にトレーニング』をするのです。
このように
『先述のバッターとピッチャーと、どちらの方が良いと思いますか?』
と患者さんとの話題にすることがあります。
みなさんは、どのように感じたでしょうか。
『痛みが気になるからYouTubeで体操やストレッチの動画を見て試しにやってみた。』
と云う方も多いと思いますが
『結局、痛みが変わらなかった…。』ならまだしも、
『余計に痛みが出た…。』
などの経験、みなさんもありませんか?
関節の可動域に、ある程度制限のある状態で運動を始めても、身体を傷めてしまうことがあります。
ストレッチや運動をしても痛みが出るような状態の疲労や筋肉の硬さには身体に負担の少ない鍼がおすすめです。
ある程度の制限を鍼で解除してからの運動をおすすめします。
このバッターがプロ2年目の日本シリーズで見せた涙は初々しく純粋で『美しかった』と思います。
色々な事が込み上げてきて思わず零れた涙。
とても共感してしまいます。
このまま純粋に歩んで欲しかったと思いましたが…
ずっとずっと『執着』していたのが残念でなりません。(本当の所は本人にしか分かりませんが…)
先日も誰かのお話で
『許せないのは仕方がない。でも自分のために相手を許す。そして相手のために祈る。』
と云う言葉が出てきて、とても感銘を受けました。
『執着』していては先に進めません。
世の中は絶えず流れているのに頑なにその場に『留まり続ける』ことになってしまいます。
このエピソードをお話させていただく時には
『ベテランなりの賢く効率的なトレーニングのススメ』と
『執着してしまっては先に進めませんょ。』と2つの濃いお話があります。
年齢を重ねると、耳の痛い話かも知れませんが…(^^;
健康になるための努力が、却って自分を壊してしまうと云う矛盾。
ズル(賢く)ではなく、賢くスマートにいきましょう。
くれぐれも気を付けたいですね。